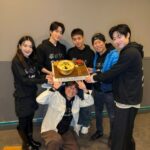(オフィシャルインタビュー)
色白の子供のように澄んだ表情の裏に一歩暗い気運が通り過ぎる。俳優ソン・ジュンギは生まれつきの美少年の顔でスクリーンを駆け回ってきたが、ただ明るいだけのことはなかった。彼の明るさは純粋と無知ではなく情況を全て知っている、むしろあまりにも多くの知り過ぎている人間の苦味を感じさせる。そのような意味でドラマ「ヴィンチェンツォ」(21)や「財閥家の末息子」(22)で多少冷たくてシリアスな側面を披露したのは、もしかしたら自然な歩みのように見える。『このろくでもない世界で』(23)は俳優ソン・ジュンギの最も重くて暗鬱な映画として記憶される作品だ。本作で彼が演じたチゴンは欲望さえ乾いてしまった、空っぽの人物だ。ソン・ジュンギはそのひどい虚無を表現してみたいという、俳優としての強烈な熱望で今回の作品を選んだ。魂まで沈む闇を渇望する俳優の瞳は、皮肉にもきらめいている。
-初めてカンヌのレッドカーペットを踏んだ。
ソン・ジュンギ(以降ジュンギ):皆こういう時「光栄で実感がわかないし緊張する」と言っていたが、そのようなありきたりな表現をなぜしてしまうのかがわかった。その言葉通りの心境だ。カンヌに出品すると言った時、「そうなのか」と意識もしなかった。正直「まさかカンヌに行けるの?」と考えていた。2月初めからハンガリーのブダペストで「ロ・ギワン」(24)を撮っていたが、撮影の真っ最中にカンヌの招待を受けたという話を聞いた。『このろくでもない世界で(仮題)』で来られてとても感謝してやりがいを感じる。本当に苦労して撮影した、意味のある作品なので大きなプレゼントをもらった気分だ。特に未来の巨匠を紹介する、ある視点部門に招待されてとても嬉しい。カンヌで初めて観たくて、まだ試写を観ていない。
-『このろくでもない世界で』に出演を決めたポイントは?
ジュンギ:知人と話していて別作品の提案を受けて、慎重に断ったことがあった。「じゃあ、あなたはどんな映画をやってみたいか」と尋ねられて、本当に深くて暗い映画をやってみたいと話した。すると「主人公ではないけれど」と言いながら渡されたのが『このろくでもない世界で』だった。最初のバージョンの脚本は本当に疲弊していた。このシナリオを書いた人は本当に大人に対する期待と希望がないな、という気がし、どんな人がこのような脚本を書いたのかが気になったのが始まりだった。改めて振り返ってみると何かを欲していたところ、ちょうどやりたい役が来て、それを掴み取ったという感じです。
-「釣られる」というのが映画でも重要な行動の一つであるだけに過程も尋常ではない。そのように会った監督の第一印象はどうだったか。
ジュンギ:会うやいなや、「どれほど大変な人生を生きてきたのか」と尋ねた。(笑)幸い監督本人の経験談ではないと聞いて安心した。不思議なことに、劇中の登場人物の姿を少しずつ持っている方だった。揺れ続けるヨンギュ(ホン・サビン)のようでも、腹違いの妹であるハヤン(キム・ヒョンソ)のような面もあり、本人の中の様々な姿を繊細に引き出すことができる監督だという印象だった。
-チゴンはどんな人物なのか。
ジュンギ:表面的には地元の犯罪組織のリーダーだ。偶然ヨンギュをみかけて、自分の幼い頃を思い出し、まるで鏡を見ているような気持ちにとらわれ、関わり始める。問題は、それがヨンギュに役にほんとうに役に立つのか分からないということだ。撮影しながらも、この部分を悩みながら撮った。チゴンは欲望が去勢されてしまったように何も望むことがない人だ。ただ生きながらえているから生きている人。
-劇中でも「生きている死体」という表現が出てくる。
ジュンギ:そうだ。生きることに虚しさを抱えており、万事無気力だ。命令された仕事だけを遂行する機械のようというか。ヨンギュはチゴンに会って変わるが、チゴンもヨンギュに会って変わる。そのような点をどのように表現するか、監督と多くの話を交わした。結局、答えはシナリオにあったよ。シナリオにあることをできるだけ忠実に表現しようと努力した。
(2ページに続く)