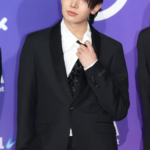かつて半導体分野で世界を席巻した日本の名だたる企業が、そのお家芸からの撤退や縮小の憂き目を見た。そんな状況にもかぎらず、半導体部門でサムスンは突出した収益をあげた。まさに「時代は変わる」である。
 『二十五、二十一』ではIMF危機で影響を受けた人たちが描かれていた
『二十五、二十一』ではIMF危機で影響を受けた人たちが描かれていた
IMF危機の優等生
日本の半導体メーカーはメモリー(パソコンの中でデータを記憶したり読みだしたりする部分)の生産では1980年代半ばから世界のトップを走っていて、サムスンも1990年代の初めに技術料を払ってでも日本の企業と提携を結びたいとやっきになっていた。しかし、日本のどの企業もサムスンの申し出を門前払いした。
その屈辱は痛手だったが、逆にそれがバネになった。
サムスンはアメリカで半導体に関わる技術者や研究者を大量にスカウトし、「日本を絶対に追い越す」をスローガンに企業が一丸となって新しい技術の追求に取り組んだ。その成果が、日韓の逆転現象を生んだ。
それ以後も、サムスンは大胆な投資と集約的な研究・量産システムを両輪として果敢に突っ走った。
何よりも、スピードが売りだった。素早く需要動向をつかんで短期間に開発から量産にもちこむ速さは他の企業では真似ができなかった。ここにも、意思決定から行動までが早い韓国人の特性がよく現れている。
半導体で大成功をおさめたサムスンが、次の基幹商品として狙ったのが携帯電話機だった。携帯電話機は最先端技術の結晶ともいえる商品だが、どの基幹部品に関してもサムスンは高い技術力をもっていた。絶対に成功するという確信をもって、会長の李健熙(イ・ゴンヒ)は携帯電話機事業に参入した。
しかし、当初は不良品に悩まされ、このままではサムスンのブランド名に大きな傷がつくのも間違いなかった。
すると、李健熙は不良品が出た機種を15万台も工場の一角に積み上げ、社員が見守るなかで一気に燃やした。
「これが今の自分たちの実力だ。こんなことが二度とあっていいのか」
工場に李健熙の檄が響いた。
自分たちが生産した商品が無残に焼かれる姿を見て、社員は誇りを取り戻すために何をすべきかを肝に銘じた。
サムスンのその後の飛躍はめざましかった。この部門でも「速さは美徳」という概念が徹底していて、消費者のニーズを素早くつかんで機能に生かし、大ヒット製品をタイミングよく生み出した。
こうしてサムスンは「IMF危機の優等生」と呼ばれ、世界的な大企業に成長していった。
(終わり)
文=康 熙奉(カン・ヒボン)
『二十五、二十一』で描かれた韓国のIMF危機とは何か(第1回)
『二十五、二十一』で描かれた韓国のIMF危機とは何か(第2回)
『二十五、二十一』で描かれた韓国のIMF危機とは何か(第4回)